- お金のこと
長期優良住宅の家
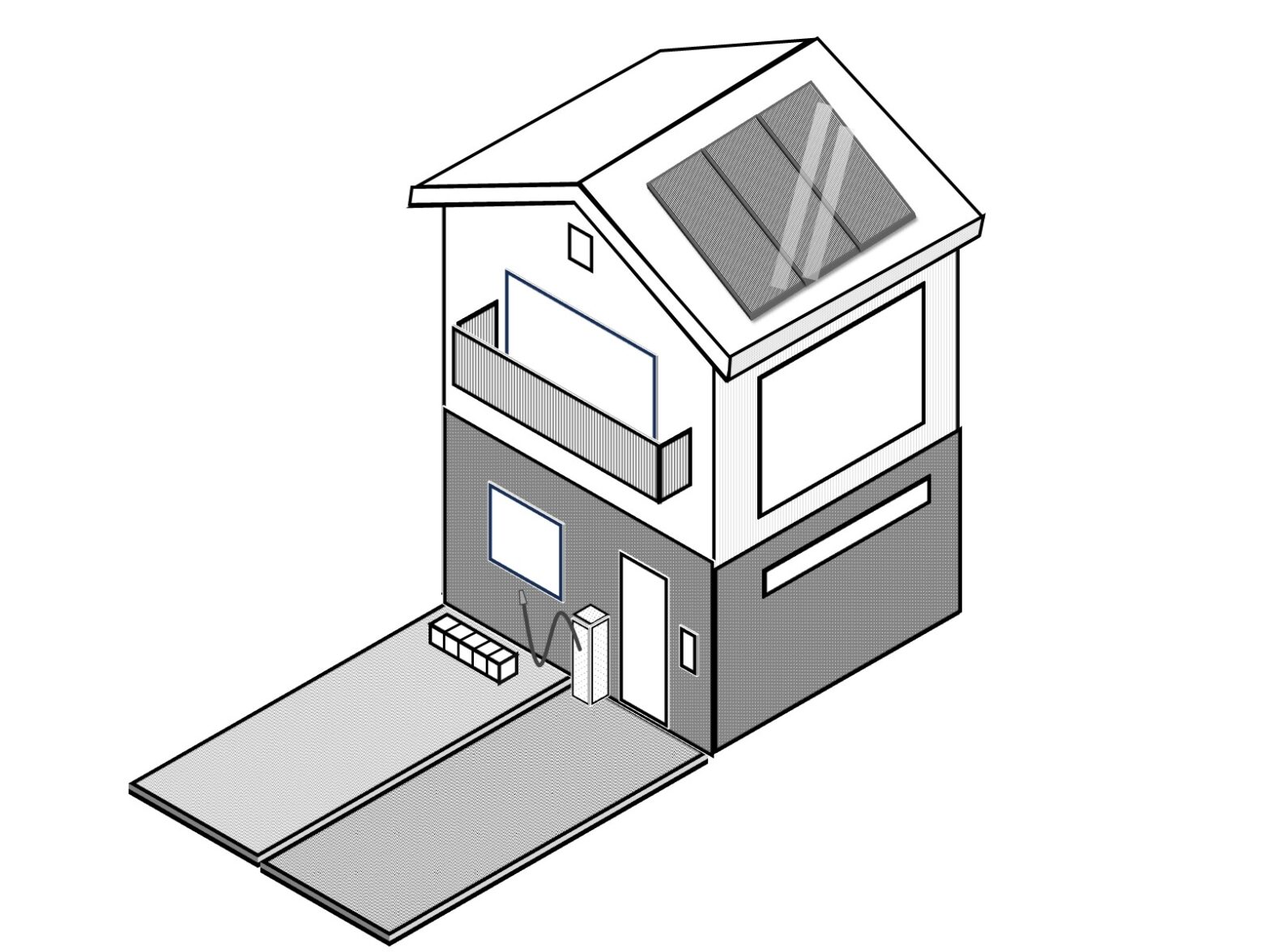
マイホームを建てるなら一生もの!!という覚悟で、長く住めるように設計したいですよね。
そこで頭の中に出てくる言葉は『長期優良住宅』
長期優良住宅とはどんな家の事を指すのでしょうか?メリット、デメリットもあるようです。そこで、今回のテーマは『長期優良住宅』についてお話していきます。
【長期優良住宅とは】
長期優良住宅とは、国が定めた長期優良住宅認定制度の基準をクリアした住宅のことです。
1)基準項目⇒耐震性、劣化対策、維持管理や更新のしやすさ、省エネルギー性
2)長期優良住宅の優遇⇒減税、住宅ローン金利の引き下げ
※所轄行政庁に申請して認定を受けると「認定長期優良住宅」となります。
【長期優良住宅の目的】
地球環境への悪影響をなくし、暮らしの豊かさを保つ!
日本の家は寿命が短く、世代ごとに家を建てて住宅ローンの返済が行われるなど経済面で
暮らしの豊かさを実感しにくい現状です。また、住宅を壊す際には大量の廃棄物が生じ、家を建てるたびに多くの資材やエネルギーが使われてしまいます。
⇒この課題の解決策の一つとして『長期優良住宅』の考えがあります!

【メリット】
①快適かつ安心できる家に、世代を超えて住み継ぐことができる
例)
耐震性を満たすことで、大きな地震でも家の損傷が抑えやすくなり、住み続けるための改修も容易に行えます。 また、省エネ性を満たすと断熱性が高まり、エアコンなど空調機器の効きが良くなるため、少ないエネルギーで夏は涼しく、冬は暖かく過ごせる家になります。
②減税が受けられる
《住宅ローン減税》
年末時点の住宅ローン残高の0.7%(上限4,500万円)を、最大で13年間所得税から控除できる制度です。
住宅ローン控除(減税)の控除額上限(年間)
・長期優良住宅・・・35万円
・一般住宅・・・21万円
※年末のローン残高の0.7%もしくは35万円という設定があるため、一般住宅の控除限度額は273万円です。 しかし、長期優良住宅の場合は控除限度額が455万円まで拡大されます。
つまり、一般住宅と比べ年間でおよそ15万円の差が出るのです。
《不動産取得税》
不動産取得税とは、不動産を購入した際にかかる税金で、一般的な計算式は以下のとおりです。
不動産取得税(建物)=(固定資産税評価額-1,200万円)×3%
一般住宅の控除額は1,200万円ですが、長期優良住宅の控除額は1,300万円に拡大されます。
例) 建物の評価額を2,500万円として計算してみます。
・一般住宅:(2,500万円-1,200万円)×3%=390,000円
・長期優良住宅:(2,500万円-1,300万円)×3%=360,000円
数万円の差ではありますが、長期優良住宅にすることで減税を受けられます。
《登録免許税》
登録免許税とは、不動産を購入する際の所有権登記にかかる税金です。
長期優良住宅では以下の税率が適用されます。
| 税率 | 税率 | |
| 登記の種類 | 一般住宅 | 長期優良住宅 |
| 保存登記 | 0.15% | 0.1% |
| 移転登記 | 0.3% | 0.2% |
住宅の評価額を4,000万円として計算してみます。
・一般住宅(保存登記):4,000万円×0.15%=60,000円
・一般住宅(移転登記):4,000万円×0.3%=120,000円
合計額:180,000円
・長期優良住宅(保存登記):4,000万円×0.1%=40,000円
・長期優良住宅(移転登記):4,000万円×0.2%=80,000円
合計額:120,000円
評価額4,000万円の住宅の場合、合計60,000円の減税効果があります。
《固定資産税》
不動産を所有している場合、毎年納めなければならない税金です。
固定資産税は3年間のあいだ、1/2に軽減されますが、長期優良住宅であれば、軽減期間が5年に延長されます。
新築住宅購入時の固定資産税の計算式
固定資産税(建物):評価額×1.4%×1/2
評価額が3,000万円の場合「3,000万円×1.4%×1/2=210,000円」
3年後には1/2の軽減措置がなくなり、固定資産税が増えてしまいます。
長期優良住宅であれば、軽減期間が5年あるため、その分の金額を抑えられます。
③住宅ローンの金利が下がる
長期優良住宅の場合、住宅金融支援機構と民間金融機関が共同で提供する住宅ローン【フラット35】のうち、 【フラット35】S(金利Aプラン)および維持保全型、およびその2つの併用で金利引下げを受けることができます。
④地震保険料の割引がある
耐震等級2なら30%、耐震等級3なら50%の割引率が適用されます。
⑤補助金制度を利用できる
性能に優れた木造住宅を新築・購入すると補助金が交付されます。
【デメリット】
①申請に費用がかかる
長期優良住宅制度を申請するときには、認定申請書や複数の添付書類が必要です。 書類の作成や代行申請に別途費用がかかるケースが一般的です。
②建築コストが割高になる
優れた住宅性能を確保するには、構造部材や住宅設備はグレードが高いものを選ぶ必要があるため、 一般的な住宅と比べると建築コストは割高になります。
③メンテナンス履歴の作成・保存が必要
長期優良住宅制度の認定を受けるには、申請時に維持保全計画を立て、 建築後はその計画を適切に実施する必要があります。
《まとめ》
長期優良住宅にはメリット・デメリットがあります。 建てた後に後悔しないために、少々複雑ではありますがしっかりと制度内容、費用を把握したうえで、 自分たちの家族にあったスタイルと照らし合わせ、十分に検討してほしいと思います。
長期優良住宅については、建築実績の多いハウスメーカーに相談することもお勧めです。 事例を踏まえてアドバイスを受けられます!

